No.005 〜 読譜のコツ 〜

読譜のコツ〜調性編②〜

by Nesteg Music Group 調布教室講師
こんにちは、調布ピアノ教室です。
調布ピアノ教室の「ピアノ初心者講座」第5回目は前回の「読譜のコツ〜調性編①〜」に引き続き「読譜のコツ〜調性編②〜」ということで、調性についてお話ししていきたいと思います。
読譜のコツ〜音程編〜
読譜のコツ〜調性編①〜
読譜のコツ〜調性編②〜
読譜のコツ〜調性編③〜
ハ長調、ト長調など楽譜でよく目にすると思いますが、楽譜を見て弾いている時には漠然と「♭が1つ付いている曲なんだなあ…」と思いながら弾いていて、でも弾いているうちに「シの音に♭付けるんだった!」とか、「もはや何調だったか忘れてしまった…」なんて状況にならないように、調性(長調と短調)と調号(♭♯)について少し確認してみましょう。
調性にはルールがある?
音程編で使った図をもう一度見てみてください。
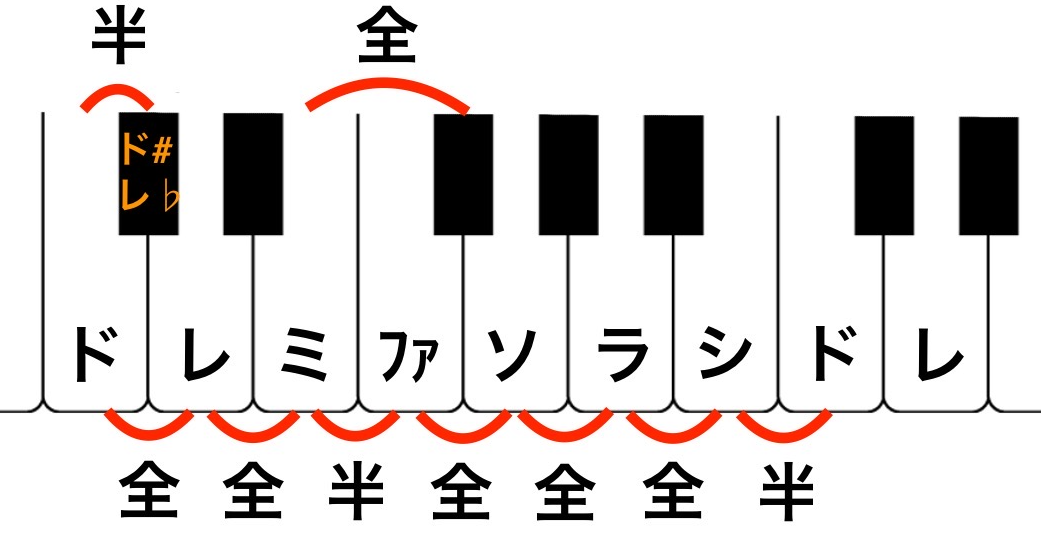
白鍵の「ドレミファソラシド」は「ハ長調」の音です。
そしてその下の音程の幅を表している箇所は「全全半全全全半」。
この「全全半全全全半」が今回のキーポイントです。
ドから数えて、「全全半全全全半」の音を使うと、ハ長調の音になります。
では、 ソから数えて「全全半全全全半」の音を使っていくと…?
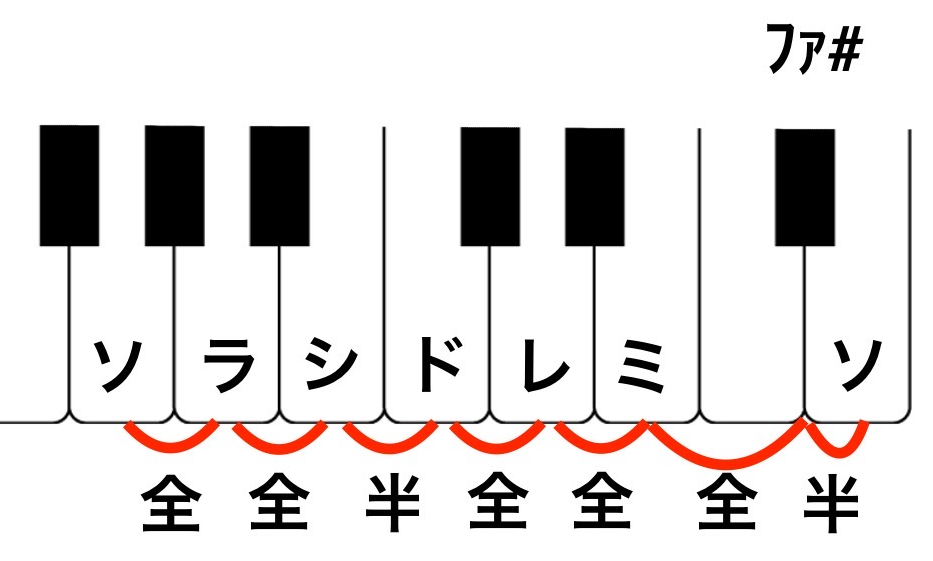
「ソラシドレミファ#ソ」
そうです、これは「ト長調」の音です。
この「全全半全全全半」という数え方をすることで、長調で使う音がわかります!
ト長調の場合、ファに#をつけてあげることで、「全全半全全全半」という並びになりますので、
ト長調はファに#をつける、ということがわかると思います。
ではもう一つ、へ長調ではどうでしょう?
ハニホヘ、ですからファから数えて「全全半全全全半」という音の並びが、へ長調の音となります。
答えは 「ファソラシ♭ドレミ」がへ長調の音です。
調号で判断するのが一番ではありますが、慣れないうちはこういった法則も補助的に使いつつ、徐々に調号に慣れ親しんでいくのも良いかと思います。
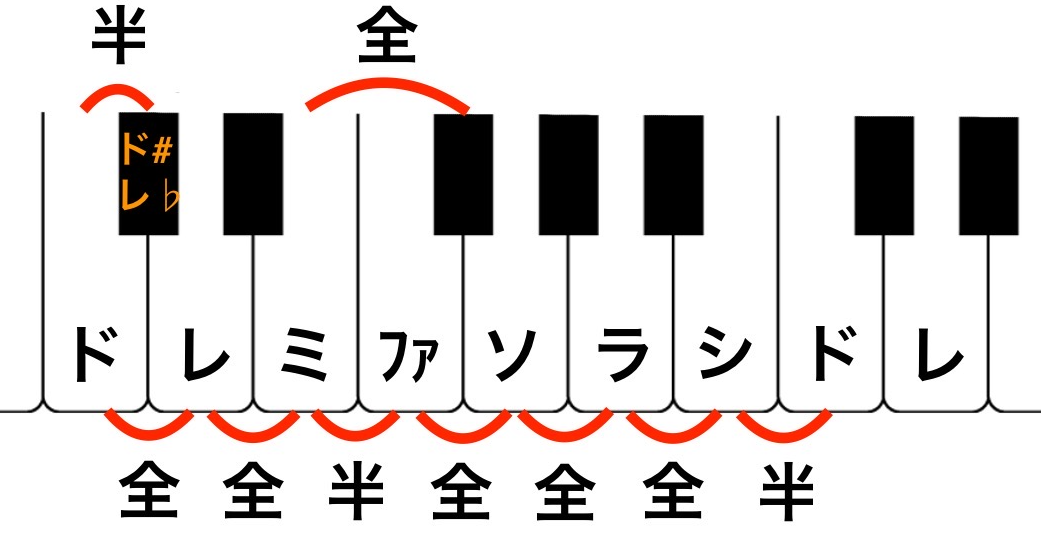
白鍵の「ドレミファソラシド」は「ハ長調」の音です。
そしてその下の音程の幅を表している箇所は「全全半全全全半」。
この「全全半全全全半」が今回のキーポイントです。
ドから数えて、「全全半全全全半」の音を使うと、ハ長調の音になります。
では、 ソから数えて「全全半全全全半」の音を使っていくと…?
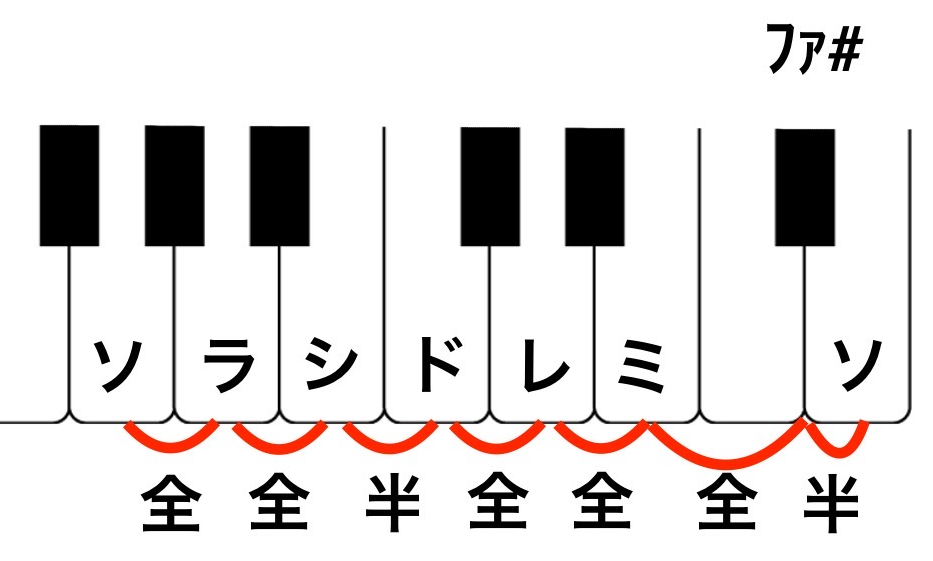
「ソラシドレミファ#ソ」
そうです、これは「ト長調」の音です。
この「全全半全全全半」という数え方をすることで、長調で使う音がわかります!
ト長調の場合、ファに#をつけてあげることで、「全全半全全全半」という並びになりますので、
ト長調はファに#をつける、ということがわかると思います。
ではもう一つ、へ長調ではどうでしょう?
ハニホヘ、ですからファから数えて「全全半全全全半」という音の並びが、へ長調の音となります。
答えは 「ファソラシ♭ドレミ」がへ長調の音です。
調号で判断するのが一番ではありますが、慣れないうちはこういった法則も補助的に使いつつ、徐々に調号に慣れ親しんでいくのも良いかと思います。
第5回目は調性についてでした!次回の「読譜のコツ〜調性編③〜」をもって、このテーマは一旦一区切りとさせていただきたいと思います。次回の更新もお楽しみに!
調布ピアノ教室は無料体験レッスンを行っています。調号についてお悩みの方は、ぜひお気軽にレッスンを体験してみてください!














